卒業生メッセージ
進路について
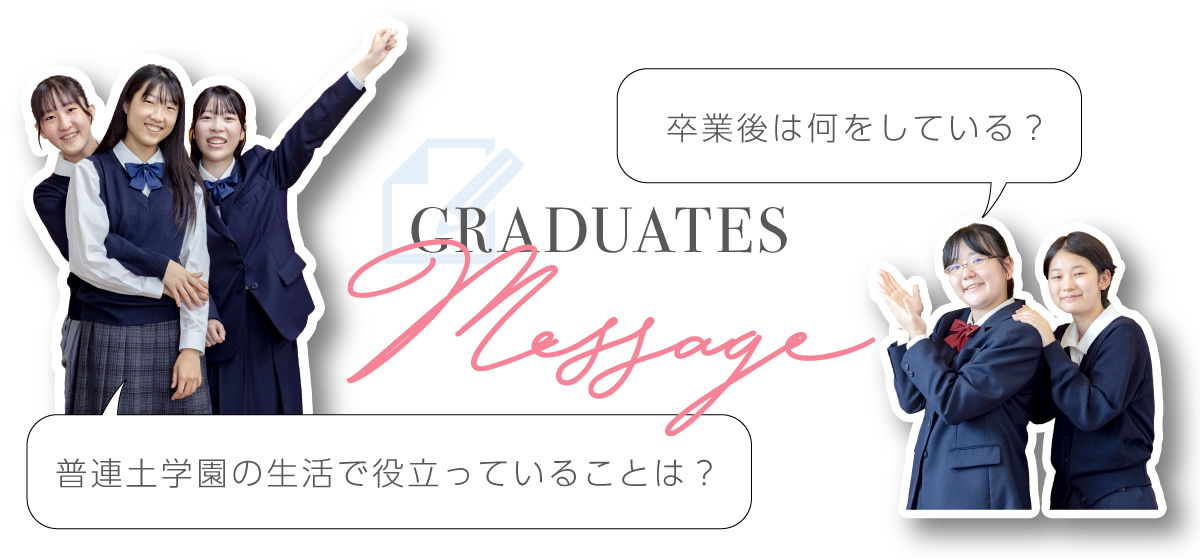

みなさま、はじめまして、99回生の迎田と申します。
私は、国際交流や英語教育に力を入れている普連土時代の環境や大学での留学経験が基礎となり、大学卒業後は外務省に入省しました。そこで、微力ながらも、主に日米外交の一端を担うことができました。その後、30歳を機に司法試験を目指し、今年で弁護士となって10年となります。企業法務や一般民事・家事、刑事事件など、国内外のお客様からの法律相談も含めて幅広く業務を行っています。
先日、受験生・保護者向けの学園主催学校イブニング説明会に参加させていただく機会がありました。事前にいただいたお題が「普連土学園での教育が今の生活にどう生きているか」というものです。その際、依頼をいただいた浜野教頭先生から、「近年、女子校は人気がない、ミッションスクールであることもさほど評価されない、キャリア教育にも力を入れ、変動する社会で生き残る力をアピールする私立校に評価が集まる傾向がある」と伺いました。
しかし、先生は、同時に、「普連土の卒業生は、時代の変化にかかわらず社会の色々な場面で人と協力して生きていく本質的な生きている力を養っているように思う。相手の価値を認めつつ、耳を傾け協力する姿勢を持つこと、また、仕事に正直に誠実に取り組むことが自然に身についていることが、人からの信頼を受けるのにつながっているのではないかと多くの卒業生から感じている点である」という趣旨のお話も伺いました。
なるほど、先生のおっしゃるとおり、同級生をはじめとする卒業生を思い返してみると、人を押しのけてまで勝ち残ることを目指すのではなく、高い共感力と誠実さ、謙虚さをもって人と関わろうとする姿勢を大切にしている人が多いことに気づかされました。実際私も、弁護士として最も大切にしていることの一つに、傾聴があります。
そこで、自分なりに普連土の教育理念を考えてみました。俗に言う言葉一言でいえば、普連土の教育理念の根本は、「豊かな『人間力』の形成」ではないかと思います。人格が作られる多感な時期に、正直かつ誠実であること、共感力をもつこと、そして謙虚であることの大切さは、学園の中で折にふれていろいろな形で教えていただき、これらは、不十分ながら、自然と身につけてきたものだと確信しています。これらの姿勢は、いくら時代が変わろうとも、社会の中でしなやかに、自分らしく生きていく上で非常に重要な力となるもので、時代を生き残る技術のみを教える学校では、決して身につかないものではないかと思います。
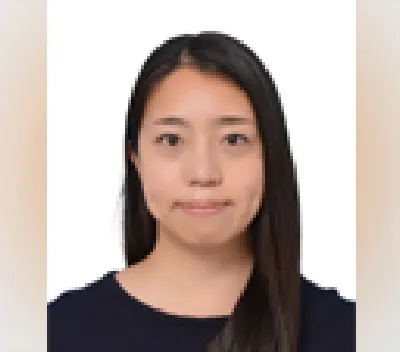
今回、普連土学園のwebページにて卒業生として寄稿させていただくことになり、改めて自分の卒業後の足跡を思い返してみました。
私は普連土学園を2000年に卒業後、慶應義塾大学の理工学部管理工学科で学び、2004年に大和総研のSE(システムエンジニア)として就職しました。
システム開発からプロジェクトマネージメントまでさまざまな立ち位置を経験後、2012年に仕事の関係でロンドンに赴任し、現地のシステム会社に在籍しました。その時の経験から『私が作るシステムを使う方々の業務をもっと理解したい』という思いが芽生え、10年間のSEのキャリアから、三菱UFJモルガン・スタンレー証券の事務部門へ転職しました。
事務部門ではルーティーンの事務を日々行いつつ、システムやプロセスそのものの改善、新しい商品への対応など、前職の経験を活かして、事務方とシステム部門や企画部門の方々の間でそれぞれの表現を『翻訳』しながら様々な提案を行う5年間を過ごしました。
証券会社での勤務を通じて、自社のプロセスを改善するだけにとどまらず、より金融業界全体に関わりながら良いサービスを届けたいと考えるようになり、現在は金融機関向けのサービスを提供する外資系の銀行にて、アカウントマネージャーをしています。
振り返ってみると本当に様々な経験をさせていただき、またその経験を次の経験に活かす機会をいただきながら、これまでを歩んできたと実感します。
それぞれのステージは楽しいことだけではなく、苦しいこと、壁にぶつかる場面ももちろん多々ありました。
それは仕事自体が難しいものである場合もありましたし、人間関係に悩んだり、自身のキャリアや人生について焦心したり、多様な状況があったと記憶しています。
しかし壁にぶつかるたびに、周囲の方々からアドバイスをいただき、活路を見出してきました。その時にお世話になった方々とは、職場が変わった今でも繋がりがあります。
先日、そのうちのある方と改めて話す機会があり、互いの話や近況報告をする中で
『久保さんは仕事の中で自分で考え、それを表現し伝えるのが上手い。こちらが言わんとすることを聴き取り理解する力もあり、本当に色々な立場の人と繋がっているよね』
と嬉しいコメントをいただきました。
コミュニケーション能力と多様性を受け入れるスタンス、劇的に変化する現代で変わらずに必要なこれらの基礎力を私は普連土学園で知らず知らずのうちに身につけていたように思います。
例えば
などなど…。
挙げるときりが無いのですが、当時はなんとも思っていなかった日々の経験の積み重ねが、今の私の礎となっています。
ちなみに、私自身は学生時代は決して英語が得意なタイプではありませんでしたが、2012年にロンドンに行った際に、驚くほど外国での生活や英語に特に支障なく日々を楽しむことができたのも、普連土学園での英語教育のおかげです。
この礎となる力を身につけさせてくれた普連土学園での日々に感謝しながら、これからも日々学び成長し、笑顔あふれる人生を過ごしていきたいと思います。

はじめまして、107回生の高橋と申します。私は普連土学園を卒業後、筑波大学芸術専門学群でデザインを、留学してPR・マーケティングを学びました。社会人になってからは広報職として2社経験後、現在は新潟にある朝日酒造株式会社で日本酒の広報・マーケティングに携わっています。広報は企業や商品を皆さんに知ってもらうための活動ですが、日々新しいことに挑戦できるので、約15年続けていても今でも仕事が楽しいと感じます。
この職に出会えたきっかけを考えると、高校2年の時の決断でした。元々は理系を目指していましたが、高校2年の冬に芸術系に転向することを決めました。その転向を応援してくれた普連土学園には感謝しています。
普連土学園での生活を思い起こすと、主体性を持って物事に取り組むという姿勢の礎になったのではと思います。生徒会や部(現在の委員会)、また日々の生活の中でも、自分で考えて行動に移すことをしていた記憶があります。それが多少突拍子もないことであっても、生徒の意思を尊重してくれる校風のおかげで、自由にのびのびと色々なことに挑戦し、取り組めていました。それは、今の仕事への向き合い方にも通じていると思います。
また、普連土学園ならではの体験として印象的なのは、朝の礼拝で全校生徒の前で行うスピーチです。週一回生徒が担当する曜日があり、私は2回ほど担当したかと思います。今の仕事柄、メディアやお客様の前で話すことが多いのですが、この時の経験も役に立ち、人前で話すことを抵抗なくできていると思います。
最後に、普連土学園で出会えた友人は、かけがえのない財産です。卒業から20年以上経ちますが、今でも仲の良い友人が多数います。そういった存在になりえたのも、普連土学園の中で6年一緒に育ったからこそだと感じています。

103回生の森真由子と申します。
私は内科医で、神経内科・リハビリテーション科を専門とし、大学病院で診療や研究をした後、現在は神経難病の方への在宅診療を行なっています。
また2009年からは普連土学園の学校医として、生徒さんたちの健康を守る仕事も行っております。
普連土学園在学中は、いわゆる「勉強」や「知識」として授業で学んだことはたくさんありますが、それ以外に、現在の医師としての仕事に通じる、先生や友達を通して学んだ、私の考える「普連土の精神」についてお伝えしたく思います。
一つは、「人とのコミュニケーション」です。
普連土では、物事を決める際、じゃんけんや早い者勝ちはありません。生徒同士話し合って決めます。例えば係りを決める時、初めは自我が出て「これやりたい!」「あれやりたい!」になりますが、友達の意見を聞き、自分の意見も述べ、「今回は別のことでもいいかな」「今回譲ってもらったから、次は私が譲ろう」と、お互い納得し、気持ちよく物事が決まります。
こういったことは、仕事の場面でも大きく役立っています。医師の仕事は決して一人ではできません。まず、患者さんや家族の気持ちに耳を傾けること、そして看護師、薬剤師、療法士、ソーシャルワーカー、病院事務など、みんなで力を合わせて初めて良い診療ができます。
二つ目は、「奉仕の精神」です。学校活動の中に、奉仕をすることがたびたびあります。キリスト教精神に基づき、見返りや報酬を求めず、仕事をすることです。
医師の仕事は、時間や労力がとてもかかることもありますが、それ以上に、人の命を預かる大変重大な責任のある仕事です。「ありがとうと言われたい」「この仕事の報酬はいくらか」などど考えていては、この仕事は務まりません。目の前で困っている患者さんに、自分は何ができるか、何がベストかを考え、少しでも症状が改善するよう力を尽くすことが、神様が私に与えてくださった役割だと思っています。
しかし、私も人間ですから、患者さんの症状が改善し、笑顔が見えると、あぁ、役に立てて良かったと安心し、また嬉しく思います。
三つ目は、「個々を大切にする」ことです。
学校では、成績の順位は出ません。自分がどのくらいの順位か、全く分かりませんが、通信簿で自分がどのくらい頑張れたか、自己評価はできます。人と比較することは意味がないこと、それぞれの個性を大切にすることを、先生や学校生活を通して学びました。
こういったことは、受験勉強やその後、社会に出ても、困難にあった際に、それを乗り越えられる原動力になるのではと考えます。
最後に、「感謝する心」です。
聖書の言葉でも出てきますし、学校生活でも「感謝」という言葉は、よく耳にし、自然と身につきました。
いつも、一緒に働く医師やスタッフ、患者さんやご家族に、「ありがとう(感謝)」の気持ちで接するよう心がけています。
聖書(口語訳)に「あなたの若い日に、あなたの造り主を覚えよ(伝道者の書12章1節)」とあります。12歳~18歳という人格形成の大切な時期に、時代に流されることのない「普連土の精神」に触れられたことは、大きな恵みでした。
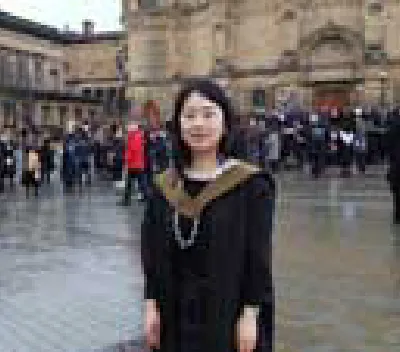
はじめまして。111回生の大浦佐智子と申します。
在校生および受験生の皆さんとご家族に、普連土学園で過ごした日々が私の人生にどのような影響を与えたか、そして今も与え続けているかを僅かながらでもお伝えできたらと思います。
私は普連土学園を卒業後、慶應義塾大学で政治学(ゼミは社会学)を学び、重工業メーカーに入社。総務部で株主総会運営や取締役会事務局業務、広報・IR部で新聞広告、テレビCM制作など広告宣伝とコーポレートブランディング業務に携わりました。入社11年目に普連土学園に在学していた頃から念願だった海外留学を実現しようと思い、退職してスコットランドの大学院へ入学。帰国後はPR会社に勤務しています。
6年間で特に私の印象に残っているもの、普連土学園に感謝していることは大きく3つあります。
ネイティブの先生が3人常駐するなど、普連土学園は英語学習の場として非常に恵まれていました。日本人の先生がABCから基礎文法を丁寧に教えてくださると同時に、Englishという授業ではネイティブの先生が劇やゲームを交えながら、自然な言い回しや正しい発音を遊び感覚で教えてくださいました。授業以外にもEnglish Lunch(全学年が任意で参加できるネイティブの先生と英会話を楽しみながらのランチ)、タスマニアのホバートにある姉妹校との交流など、日本にいながらにして生の英語に触れる機会が数多くありました。また、自分でテーマを決めて書いた英作文を先生は毎回丁寧に添削してくださり、自分が期待する以上のサポートを常にしていただきました。
普連土学園の英語教育は日本で受けられる最高峰の教育だったと、今改めて思います。そして、先生方が1つ1つの授業を準備する手間と労力がどれだけかかっていたかと思うと頭が下がります。
おかげで英語の発音はネイティブからも褒めてもらえることが多く、大学院の英語に関する入学資格要件をクリアできたのは普連土学園で基礎をきっちり身につけたからだと思います。
委員会活動も思い出深い活動の1つです。生徒会を始め、選挙管理委員会、図書委員会、宗教委員会など複数の委員会が存在し、必ず1つの委員会に属して学校運営に関わる仕組みは、どうやって自分たちの学校生活をより充実したものにしていくかを自ら考え、実行する機会になっていたと思います。また、年に数回ある大掃除、毎日の掃除は教室だけでなくトイレ掃除まで自分たちでやっていたことが、当時はありがたくなかったのですが、今になってその価値が見えてきました。自分たちが使うものは自分たちで整える、それ以前に共同で使うものは大事に扱う、基本的なことですが知らず知らずのうちに身につける機会になっていたと思います。
今でも窓ガラスを磨く際、雑巾で拭いてから新聞紙で地道にこするという普連土式を私が継続しているのも、身に着いた習慣の強さを感じる瞬間です。
自分の置かれた状況を自分ゴト化して考える。時々目をそむけてしまうこともありますが、「他人事にする言動は恥ずかしいこと」という意識を持っていられるのは、普連土学園の日々の生活によるものだと思います。
毎朝の礼拝は先生方、同級生、先輩後輩の話に耳を傾ける貴重な時間でした。中でも忘れられないのは、畠中ルイザ校長(当時)がおっしゃった「You are lucky ones.」という言葉です。先生はこれを話の最後、締めくくりの言葉として使われました。「恵まれた環境に生まれたあなた達は、その恵まれた状況と自分の持てる力を、人のためにどう使いますか」という問いかけだったと解釈しています。
普連土学園は奉仕活動に携わる機会が多くあります。雑巾を手縫いして障碍者施設に寄付したこと、収穫感謝の時期にはリンゴとミカンを持ち寄って病院に届けたことなど、今でも教室に満ち溢れる果実の香りと一緒に思い出すことがあります。
正直、卒業から20年近くたってもこの問いに対する私の答えは出ていませんし、行動に移せていると100%自信を持って言うこともできません。しかし、「自分がやることは誰かのためになるだろうか」ということは、折に触れて考えるように意識しています。世界を変えるほどのことはできなくても、周囲の人に小さなことでも還元できる人生を歩みたいと思っています。
6年間を振り返ると思いがこみ上げてきて、書ききれないことが数多くあります。
思いがこみ上げてくる、心が温かくなる思い出が沢山ある、それだけ幸せな6年間だったと思います。そして幸せな記憶が今を生きる力になっています。
大学院留学時代、とても嬉しいことがありました。
休暇中にパリ航空ショーを訪れ、前年にロケット甲子園で優勝し、国際大会出場権を得ていた理科部ロケット班チームMERN(メルン)メンバーと恩師に再会できたことです。女子だけのチームで参加しているのはMERNだけで、海外の高校生と並んで立つ後輩たちがとても誇らしかったです。
これだけ多くの人の善意に囲まれ、全力でサポートしてもらえる期間は人生において多くありません。12歳~18歳を普連土学園で過ごす皆さんの人生が、私と同じように、幸せな記憶が苦しい時も一歩ずつでも前に進む力になることを一卒業生として願っています。